|
写真論・光。

光とは。
光は波だ、いや粒子だという論争が続いていた。古典力学で知られるニュートンもこの論争に加わっている。その後量子論(1900)が、そして量子力学へと物理学が発展、アインシュタインが特殊相対性理論(1904)を発表、光は粒子であると同時に波でもあるとした。つまり、どちらも正解となった。光は電磁波のひとつであり、エネルギーの一形態にすぎないという。光の速度は真空中秒速30万キロメートル、これ以上速く移動するものがないことから絶対速度と呼ばれるが、本当のところはまだ分かっていないともいわれる。モノクロ撮影では、赤や緑のフィルターをつかうことが多いが、この原理はフィルター色以外の光をフィルターが吸収することによる。このとき吸収された光エネルギーは熱エネルギーに変換され、大気中に放出される。フィルターを使用する場合、しばしば発熱を感じるのはこの理由による。電磁波のうち、人間が認識可能な部分を可視光線、つまり、光と呼んでいる。あくまで人間の都合による分類である。光は、それ自体は見えない。1.光源を見る場合と2.何かに反射した場合だけ見える。また、例えば昆虫は紫外線、マムシなどは赤外線で対象を認識するとされる。人間は色彩を見分けるが、犬、牛、ネコ、馬などは色彩を認識しないと考えられている。詳細は「眼」の項に譲る。
光の種類
光を光源別に分類すると三つに分類できる。第一は熱によるもので、黒体輻射ともよばれ、太陽光がこの代表例である。また、ロウソクなどの燃焼光もこれによる。これは温度により色彩が変化する。色彩を示すとき白金の温度を基準としたのが色温度だが、ちなみに太陽表面温度は、摂氏6000度とされる。ストロボ(Speed
Light or Flash Light)もここに分類される。
第二は原子発光である。たとえば蛍光灯では、蛍光管内で電磁波エネルギーが蛍光物質の原子を発光させる。ネオン管発光やダイオード発光もおなじである。ネオン原子は固有の赤色を発光する。普通の会話では、青色でも白色でもネオンサインと呼ぶのは妙だが、これは語学の問題であろう。原子発光には独特な基本色があるから、カラー撮影では色補正が必要となる。第三は、放射発光でシンクロトロン発光ともいう。これは強烈なエネルギーをもち、超LSIの製造時の焼き付けなどに使用された。撮影に使うことはないだろうから、前の二種類の光を記憶すればいい。原子炉の放射線遮断用水炉が発光するのは第三の特殊な例であるという。
光の印象
光は直進する。何かにあたると反射する。透明物体にあたれば透過率に従い透過する。このとき密度が異なると屈折する。これがレンズの原理である。また、半透過物の場合、光は散乱を起こす。すなわち、平行性を失いあらゆる方向へ進行する。結果として距離により光量が減少する。逆にいうと光量は平行性が保たれる限り変化しない。この例としてレーザー光線がある。身近な例では劇場などのスポットライトがある。これらについては後述する。撮影に使用する光には、散光と直射光と、両者混合がある。この性質を知っておくと効率がよい。
直射光と反射光
散光とは散乱光のことであり、印象は日陰で撮影する場合や、障子やカーテンを透過した光で明るい室内などの印象を想像すればいい。散光には、透過光によるものと、反射光の二種類がある。(実際の撮影では、透過光はデフューズとして半透過物を通過させて、反射光は反射板に光を反射させて使う。)
仮に太陽直射光が障子にあたっており、それを脇に人物がいたとする。光は障子紙(半透過物)を通過する時、あちこちへ散乱して方向を変える。すると、方向を変えた光が、陰の部分をも照明するから、明暗の比率が低下してやわらかい印象となる。このとき主たる光源(撮影に使う最も明るい光源)は障子となる。より正確にいうと障子紙のうち光があたる部分である。仮にこのとき障子が10メートル四方だったとしても、光があたる部分の面積が1メートル四方であれば、光源の大きさは1メートル四方の大きさとなる。(こういった場合、撮影現場では光源が障子紙に移動したと考えれば、わかりやすい。)
人物が障子に近づくと、光源は相対的に大きくなるから、散光効果がより明快となる。また、白い紙や布などに光を反射させても、同じことになる。散光とは、光線の平行性を奪う結果である。そのため散光では陰ができない。あるいは輪郭線がないか非常に不明快となる。陰の輪郭線が明快な場合は散光でなく直射光である。
つぎに直射光を考えてみる。直射光は、例えば被写体となる人物が太陽光線をほぼ正面から浴びて撮影する場合を想像すればいい。周囲からの反射光にくらべ、太陽光が強く、明暗の差が大きく、陰が明快となり、くっきり、はっきりした印象になる。また、陰の輪郭がはっきりする。複数の陰の一部から、それぞれ陰を作る物体部分に対して光源の方向へ線を引き、これらを延長してやると、その交点に光源が存在する。交点の数と光源の数は等しい。太陽や月の光は完全平行だから交点はできない。もし交点ができれば太陽や月の光ではない。この理由は幾何学で証明される。また、当然ながら、陰もひとつだけである。例外として、鏡張りのビルに太陽などが反射している場合がある。しかし、鏡の反射率があるから、陰に濃淡の差ができる。
コントラスト(明暗比)
コントラストとは明暗の差である。簡単にいえば明るい部分と暗い部分との光量差である。コントラストが強いとは、明部と暗部の光量差が大きいことであり、コントラストが低いとは、明部と暗部の光量差が小さいことをいう。
さて、散光での写真は、その他の条件を同じにした場合、コントラストが低くなる。印象は、おおむね、なめらかでやさしい印象となる。また上品な印象が強調される。欠点としては、印象が弱くなる。光量差が少ないからカラーフィルムの色再現性を助ける。
散光の印象とは反対に、直射光では力強い映像となる。また明暗の比率が適切であれば、被写体の立体感が強調される。また、シャープな映像が得られやすい。欠点として優雅さや情緒性、色彩の正確さに欠ける。
散光は日本画的であり、微妙な色彩相違を主題にする場合、情緒性や主観性を強調するときに便利である。これに対し、直射光は西洋絵画的、あるいは客観的な印象を与える場合に便利である。プリントであれば、直射光はモノクローム・プリント、散光はカラーのプリントを作るために便利である。以上は他項で詳述する。以上は一般的な経験則だから、あくまで参考にとどめていただきたい。
注.1
望遠レンズと散光との組み合わせでは、日本画的な、情緒性や装飾性が描き易い。直射光と望遠レンズを組み合わせると、力強い映像となる。スポーツ写真などに多用される。ワイドレンズと直射光の組み合わせは、客観性が強くなり、客観的で西欧的な印象が強くなる。散光とワイドレンズの組み合わせは、この中間の印象となるが、使い方は難しい。東洋絵画技法にはもともと光と影の概念がない。絵画との関係は他項で説明したい。

組み合わせて使う直射光と散光
実際の撮影では、直射光と散光を組み合わせて使うことが多い。主に使う光源を主光源と呼ぶ。屋外撮影では、主光源は撮影方向で異なり一定しない。たとえば太陽が人物の正面から来るような位置から撮影すれば直射光撮影だが、反対方向から撮影すれば逆光撮影となる。逆光撮影では、主光源は太陽直射光ではなく、スカイライト(後述)と、周囲の物体からの反射光となる。この場合、直射光はアクセント・ライト(装飾光)−ラインライトとして機能する。
―作例図挿入―募集中!
コントラストと感光度
直射光風景撮影の場合、モノクロフィルムでは良好なコントラストが得られる。被写体を人物に変えると、コントラストが強すぎる。カラー撮影の場合はこれが強く現れやすい。この多くは心理学的理由による。よく見慣れた被写体、たとえば人物などへは、それぞれのコントラストはこの程度、といったデータが見るものの大脳にあらかじめ詳細にインプットされている。これに反すると見るものに違和感を与える。つまり、物理学的正確さと印象の正確さには違いがあり、両者の間にズレが発生することになる。
写真を見る人の印象どおりの明度・コントラストを、ふつう期待明度・期待コントラストと呼んでいる。これらは、見る者の性別、年齢、文化、時代などで異なる。年齢だけを例にすると、印刷専門家の話では、日本の若者が暗めの肌と強いコントラストを好むのに対し、中年では、明るめの肌と低コントラストを好む傾向が見られるという。
屋外風景撮影・スカイライトについて。
屋外での直射光は光量が十分であり、かつコントラストが適切だから、シャープな映像ができる。ところが太陽光といっても単純ではない。地球は厚い大気で覆われている。太陽から発し、8分後に地球に到達した光は、大気層を通過するとき、まずアルファー線など波長の短い有害な放射線のすべてと、紫外線などのほとんどが吸収される。すなわち大気は地球上の生命を保護している。このとき光は空気、水分、塵芥などの分子に衝突して散乱する。この散乱光をスカイライト(天空光)という。
スカイライトは太陽直射光の陰を弱める。もし、直射光だけであれば、異なった映像となる。つまり宇宙空間での写真映像である。波長の短い光、すなわち青に近い色が散乱しやすい。この結果、カラー撮影では青みが強くなる。補正としてスカイライトフィルターがある。なおスカイライトの光量は思ったより強く、しばしば露出オーバーを引き起こすから無視できない。
大気が作るスカイライト
太陽光撮影では、直射光とスカイライトが混合する。スカイライトは散光だから、陰の部分を照明し、強すぎる陰の部分を補ってくれる。夜間撮影や、スタジオ撮影と異なるのはこの点である。直射光とスカイライトとの光量比は、気候風土で異なる。また、空気の濁りに左右される。また空気濃度(高度)でも異なる。東京ではこの比率はおおむね1:4となる。絞りの値に換算すると2絞り分となる。この比率は、明部と暗部の光量を露出計で計測すれば簡単に求められる。空気が濁る都会ではコントラストが低下、またカラー撮影では色濁が生じる。反対に澄んだ空気中ではコントラストが高くなる。山岳写真などで経験されるはずである。エベレストの頂上などでは、空は青というより黒に近い独特の映像となる。
空はなぜ青い
繰り返しになるが、太陽光が大気層を通過する時、波長の短い光(青色光)は散乱する。空が青いのはこのためで、他の色はほとんどそのまま地上へ届く。太陽が黄色く見えるのはこのためである。光の三原色(RGB)のうち青以外の色、すなわち緑色と赤色を加えると黄色となるからだ。雲はすべての光(RGB)を散乱させるから白く見える。空気が薄い高山などでは、散乱がないから空の色は高度、つまり、大気濃度の相違で青から黒へと変化する。空気が薄い分、スカイライトは弱くなり、コントラストが高くなる。夕方や朝方など、太陽の位置が低い場合は、通過する大気層が長くなるため、波長の短い光は届きにくく、波長の長い赤系統の色が届きやすい。朝焼け、夕焼けの理由である。
周囲からの反射光
次に実際の撮影ではスカイライト(散光)に周囲からの反射光(散光)が加わる。たとえば降雪のあとでは積雪からの反射光が強いから、これを計算に入れる必要が生じる。また、人物が黒い土の上に立つ場合と、アスファルトの上に立つ場合でも異なる。芝生の上では緑色の反射が加わるから、印刷原稿など、精密を要する場合は、色補正が必要となる。近くの建物などからの反射光も影響する。
スタジオ撮影
写真の創設期には自然光が多用されたが、現代のスタジオ撮影では、人工照明具を使う。スチール写真では、多くはストロボ(Speed
Light)という電気閃光を使うが、熱光源(タングステン・ライト)を用いる場合も考え方は同じである。ストロボと比較するとタングステン・ライトは消費電力の効率が悪い。また、熱光源の温度が低いため、カラー撮影で専用フィルムをつかう必要がある。
光量は距離の二乗に反比例する。良く知られた法則だが、これは、たとえばロウソク燃焼のように光源から、あたかも球体を作るように光が放射状に進行するときの話である。実際の撮影用器具では、点光源の背後に反射装置や、前部に集光レンズなどがつき、方向性がある。このような光源では、球体を作るように進行する光はできない。よって「光量は距離の二乗に反比例する」との法則は成立しない。
注.2
前述のとおり、光は平行性を保つ限り光量は一定である。大劇場で使うスポットライトなどでは、光源の背後に反射鏡、そして光源の前に集光レンズがついて光の平行性を保つ。その結果、100メートル程度はなれたところであっても、一箇所への集中照明が可能である。また旧日本軍用サーチライトでは、上空3000メートル以上の爆撃機を照射したとある。未確認ながらドイツの記録では7000メートルの到達距離をもつものがあったとされる。その他の極端な例では、レーザー光線があり、これは位相、つまり周波数と波長がミクロ単位まで同じ光線を照射すると、地球から月までの距離を往復し、その時間差から両者の距離を計測する、などの例がある。現在、地図作成などや、測量などに日常的に使用される。
逆に光の平行性を奪った場合には、光源から離れると極端に光量が減少する。つまり距離によって光量が極端に減少する。散光はこの代表例である。
スタジオ撮影では、直射光を使用する場合、ふつうは集光レンズつき照明器具を使用する。また、散光の場合でも、スクープライトという、一方向へのやや広い照射角度を持つ照明器具を使用する。なおスクープライトはトレシングペーパーなどの、半透過物を同時につかうことが多いが距離関係を考えずに半透過物を使用しても無益である。
ライティングの説明では、モデルの周囲をライトがぐるりと回って、どのような効果になるか説明しているものが多い。大切な知識であるが、もう一歩進め、光の種類による対象の見え方の違いと、この使い方を身につけておくとより効率的と思える。
スタジオ内の面光源
これは、発光源となる点光源からの光を、面の状態に変化させて散光を得る方法である。たとえば、写真電球と被写体の間に、半透過紙をおくと、写真電球からの光は半透過物で散乱する結果、滑らかな諧調の光が得やすい。反射光を利用しても同じである。透過させても反射させても、光源が面の状態になっているため、これらを面光源と呼ぶ。もちろん面の形は問わない。四角でも丸でも差し支えない。
―イラスト挿入―
この場合、点光源と半透過物(あるいは反射物)との距離A.次に半透過物(反射物)と被写体との距離B.が重要となる。スタジオ内では、屋外と異なり、スカイライトなど自然の補助光がない。すると光源の大きさが重要となる。たとえば小さな昆虫の撮影には、直径10センチメートルの面光源で十分だろうが、人物全身を撮影する場合は、身長ほどの大きさが必要となり、光源の大きさが不足する。すなわち、ふさわしい光源の大きさは、被写体の大きさで決まることになる。また、この大きさは被写体との相対関係で決まる。この場合の、ふさわしいとは、撮影者の意図どおりという意味である。
AとBとの長さは、図に描くとすぐに理解できるが、Aを短くすると、光源が結果的に小さくなる結果、コントラストが増加する。また、Bを小さくすると、光源は相対的に大きくなる。AとBの関係は、最終的には被写体から見て、実際に発光する面積の大きさである。最終的には、被写体から見た光源への角度の問題と理解すればよい。これで、ほとんどのライティングが理解可能となる。この原理を使い多くの商業写真家が、商品撮影などに使用する光をコントロールしている。つまり、ふさわしいコントラストを調整している。散光が強すぎればコントラストが低下しすぎ、いわゆるフラットな状態となり、立体感が失われ、直射光のみに偏れば反対の印象となる。
注3.
光源の位置により映像の印象は異なる。一般的に光源を高い位置に設定すると、昼間の印象が強くなる。反対に光源を低い位置に設定すると夜の印象が強くなる。また、これらの原則は、室内照明に多用される。建築やインテリアの専門書が参考となる。また工場や作業所では、安全確保のため明るさなどに法令の規定が定められている。一般家庭でも窓の面積などは、建築基準法の規定がある。人間と光の関係は、現実生活そのものである。
スタ ジオ内の点光源 ジオ内の点光源
人物撮影でスポットライトを主光源(メインライト)として人物背後から当てたとき、それだけでは逆光となり(人物の輪郭線が強調されることにはなるが)人物は暗くなりがちである。このとき人物前方から白い板などで背後からの光を反射させると、充分な明度が得られ、かつ整った諧調が得られる。普通レフ板というが、反射光の使い方として極めて一般的である。誤解しやすいが、面光源のもとは、点光源である。点光源の光を散乱、反射させて散光を得る方法が、面光源である。
これに反し、ロウソクの光だとか、スポットライトの光をそのまま被写体に使うと、光源は点状態だから小さい。これを点光源と呼ぶ。この場合、非常にコントラストが高くなる。レフ板などで補助光を加えるなどしないと、なかなか難しい。散光が過ぎた場合は、モノクロではコントラストが低下しすぎる。フィルム現像時間を増加するなど、適切な措置が必要となる。カラー撮影の場合は、色彩再現力が増加する。スタジオ内では、光源の大きさを調節することに加え、レフ板、他のライトの使用など、いわゆる補助光が必要となる。最大の理由はスタジオ内では空気量が少ないから、スカイライトという自然の補助光がないことによる。
注4.
どのような補助光を使用したかは、人間の眼球の反射から簡単に推理できる。人間の眼球は反射性があり、かつ球体だから周囲の光源をすべて写しこむ。これをキャッチライトというが、ここからどのような補助光を使用したかが判明する。補助光も状況を計算に入れないと、不自然さが目立つ事になる。また、眼球だけでなく、ガラス器など、反射物から相当の情報が得られる。陰の状態についても同じことが言える。
科学への貢献が大きい写真
またカメラも写真だけにとどまらず、印刷・医学など、その他、自然科学界へ重要な貢献を果たしている。近代の感光材料は、レントゲン撮影など、臨床医学に革命的な貢献を果たした。内視鏡による写真撮影や医療技術は、医学だけでなく、工業用内視鏡として新技術に、また自然災害や考古学に多大な貢献を果たしている(他項を参照)。日本でも1898年に写真大尽として有名な鹿嶋清兵衛らが、レントゲン写真を公開実験したが、時期は相当に早い。
注4.
この鹿嶋清兵衛という人物については、森鴎外による『百物語』や、白州正子氏による『遊鬼欧外「百物語」後日談』に詳しい。一度、専門書や写真博物館などへ足を運ばれるなどすれば楽しみが増えるのではないか。また、カメラの原理には、それほど大きな変化はないことに驚かれるはずである。光とエネルギーの関係は興味深いが不案内だから、専門書にあたられたい。絵画史との関係は別項に譲る。
よ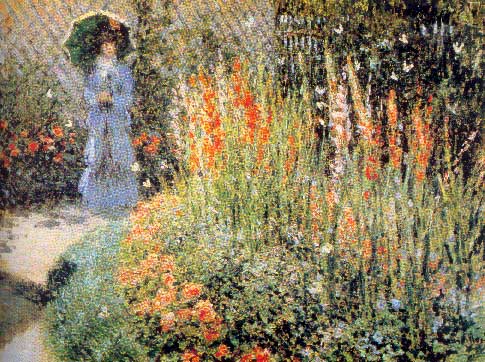 って立つ光 光と色を研究した画家モネの一作品 下 って立つ光 光と色を研究した画家モネの一作品 下
写真は光があるから対象が撮影可能となる。化学があり、光学があり、人間は写真を撮ることができる。写真はカメラと感光乳剤料という物理現象にもとづくために制約がある。だが、この制約は思うほど困難ではない。写真表現は、あくまで光と道具の使い方だと熟知したとき、対象の自由な表現が可能となり、他ジャンルと同等の資格を得る。文学が原語、絵画が平面や絵の具などに、音楽は空気振動に制限を受けるが、これらを自由に使いこなして表現が可能となっている。写真では光の知識が必要なことはいうまでない。どのように写すかは、結局、どのような光を使うかが大きな要因である。
著名写真家・菅 洋志氏は、日光東照宮やベトナムを題材に優れた写真集を多数出版されているが、アジア的風土特質を、色彩強調から鋭敏に伝えている。氏は、朝方と夕方しか撮影しないという。確かに朝陽や夕陽に照らされた原色の建築物や仏像は、極彩色の混沌からアジア的躍動感と郷愁の時間とを浮かび上がらせ、観る者を魅惑して心を奪う。また立木義浩氏はエディトリアル写真の第一者であるが、スタジオ撮影のライティングはプロであれば誰しもが感心する。これらの能力は相当の修練を必要とする。しかし、他のジャンルでも修練は必要だから本質的な相違はない。問題は写真批評や写真論であろうか。内容は優れたものが多いが、光を無視する場合が多く説得力を欠く。何故、その被写体を選択したか?の研究は盛んだが、何故、その光を使ったのか、の研究が不足している。他のジャンルでは、何故そのような技法か、たとえば文学では何故その文体か、絵画ではなぜその技法か、といった研究が当然だが、写真ではよって立つ光が無視されやすい。
映画映像監督システム
最近気づいたのだが、日本映画の衰退の原因に光の使い方知識の不足があると思えた。
現代の若者は生まれたときからテレビに囲まれ、映像経験が豊かであるから、不自然な光は無意識に見抜いてしまう。これは他章でのべる「見るという行為は大脳にインプットされた情報と比較対照して対象認識を行う」との医学的な理由による。 米国では映画監督とは別個に、映像監督がいるが、映画監督の過大な役割を考慮すると、分業したほうが賢明であろう。映画はもともと分業の上に成立する表現である。日本でもシステムを確立しないと、面白みが減少すると思える。このあたりの研究がもっとなされて良い。日本には優秀な映画のつくり手が多いのに、興行成績があがらないひとつの理由と推理している。
芸術写真が誤解した光
戦前に活躍した福原信三(1883年〜1948年)は、写真集『光と其の諧調』で著名となり、あたかも、光の美しい状態を撮影することを提唱し、日本写真史の流れを変えたように思われているが、実はそれは結果であり、論文を読む限りそのようなことは言っていない。1923年に太田黒元雄らとおこした写真芸術社刊「写真芸術」に発表された『写真の新使命』承前を読むと、可憐なほど写真が芸術になり得る条件を強調している。「音楽が音階に、詩が文学に、絵画が形に依存しているのと等しく・・・」として写真は光が成立要件であるという極めて当然なことを述べ、結論として、「例えば作曲家が音そのものとなりて・・・」といった記述に終始、どんなジャンルであっても無我の状態で作品を作ったとき、例えば写真であれば、無我の状態で光を自在に使いこなせたとき、芸術作品となると述べている。
氏は写真芸術の本質について自己の考えを形而上的、あるいは抽象的に述べているに過ぎない。これを物理的に誤解して読んだ者が、光を写すことが(実際は不可能だが)大事だとして、ソフトフォーカス・レンズを使った絵画的作風が広まったと考えられる。福原信三の作品は、この時代としてはモダンであり、スマートであり、またリッチであり、それほど光自体に拘泥したとは思えない。この作風は、氏が資生堂二代目経営者として大成したことと無縁ではあるまい。同じような誤解は西欧にもあり、1886年からピーター・ヘンリー・エマソンも科学と芸術の調和する発展を唱えて努力したが、これも、ソフトフォーカスを使いさえすればいいといった、同種の誤解が生じ、1890年に『自然主義写真の死』を著し、写真の第一線から姿を消してしまう。
光は科学
写真では、もういちど、光とその性質を検証することが大事という筆者の主張には、必ずこのソフトフォーカスを持って反論される方が多く、筆者の真意とは異なり少々残念である。要は、より科学的に写真を考えたほうが、といっているだけである。よってたつ光の豊富な知識は、決して無駄とはならない。また、レンズ光学だけにとどまらず、心理学、照明学、色彩学、建築学、物理学、医学など、最新の科学から、光をより広範に再確認する必要を唱えているだけである。現実として対象の見え方を突き詰めてゆけば、大脳生理学までが、かかわってくる事になり無邪気な反論だけではすまなくなる。
いまの写真芸術の限界が必要とする柔軟さ
たとえば電子顕微鏡の写真集を見ていて、自然の造形力に驚かされる、といった経験は多くの方々が体験されることであろう。最近の科学技術による映像には驚くべきものがある。大自然が作り出す造形は、人間の知恵をはるかに超えている。これと同じで、大自然の作る光の演出も、人間の想像を越えることがある。自然を直接に撮影する場合だけではない。人間は火を使うことで動物とは区別されるが、ヒトは夜の生活と文化を持っている。
人工照明の中に、思いもかけない光状態が発見されることもあるだろう。光に対しいつも鋭敏な感覚を研ぎ澄ませておきたいと考える。対象を見て美しいとか、感動した際には、光の状態をよく観察しておけば、同じ光の状態を再現できることになるため、表現力が増加すると考えるのが自然であろう。
必然的偶然を
どのような状態であっても、光が演出する状況を的確に把握し、その理由を解明することにより、同じ状況を再現できる能力は、難しいことではあるが、写真家の重要な仕事であろう。なにを撮るかは勿論として、どう撮るかは、ほとんどがライティングに帰結する。偶然に良い効果にめぐり合ってシャッターを押すなどといった神話からは、もはや卒業の時期にきたと思える。あらかじめの予想と計算の上で偶然は、必然に近い偶然であろう。あたかも、熟達の漁師が魚群の行動を予測して漁獲高を増加させるのと同じである。
残された課題
人類は光の喜びを十分に描き尽くしたであろうか。まだやるべきことがあるのではないか。印象派以降、絵画史は少し急ぎすぎた。印象派からシャルダンへ、再び印象派へと関心を移しつつ光の表現の階段を上ってきた。なぜ光は(ヒトの心を)揺さぶるのか。なぜ心地よいのか。もっとも素朴な問いに素直に従っていけば、おのずと開けると考える。
以上は読売新聞日曜版、『絵は風景』芥川喜好記者 が現代画家を紹介する文の一部である。これを読むとき植物がどうやって栄養を、あるいは、原子力を除くすべてのエネルギーが太陽光線の結果であること、そして特殊な生物をのぞけば、光は生命の源であるとすぐに理解できる。ついでに言えば、古代からの文明でさえ気候風土に帰結する事に思い至るとき、いわば生命の源である光が、ヒトの心に与える根源的影響を考えざるを得ない。まだまだ、やるべき事は多いだろう。芸術であってもなくてもいい、リアリズムであってもそうでなくてもいい。そのようなことは、もういいではないか。絵画でも写真でも映画でもいい。光の根本的魅力はほとんど手つかずに残されていると思えてならない。写真もまた少し急ぎすぎた。写真ははたして光の喜びを表現に十分に取り入れたであろうか。何時もの仕事であれ、光の持つ本来の魅力を取り入れるだけで内容が深まると思える。光でなぜ心安らぐのか、なぜ心を揺さぶるのか、なぜ人々をこれだけひきつけるのか、まだ,やるべき仕事が数多く残されている。芥川氏のいうように、素直な問いかけに素直に従えば、答えは自然と見えてくるはずである。
写真と無常へ インデックスへ戻る
インデックスへ戻る
|



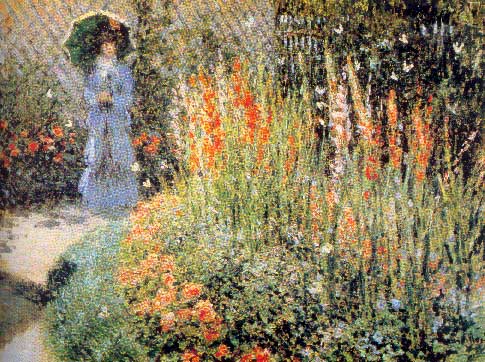 って立つ光 光と色を研究した画家モネの一作品 下
って立つ光 光と色を研究した画家モネの一作品 下